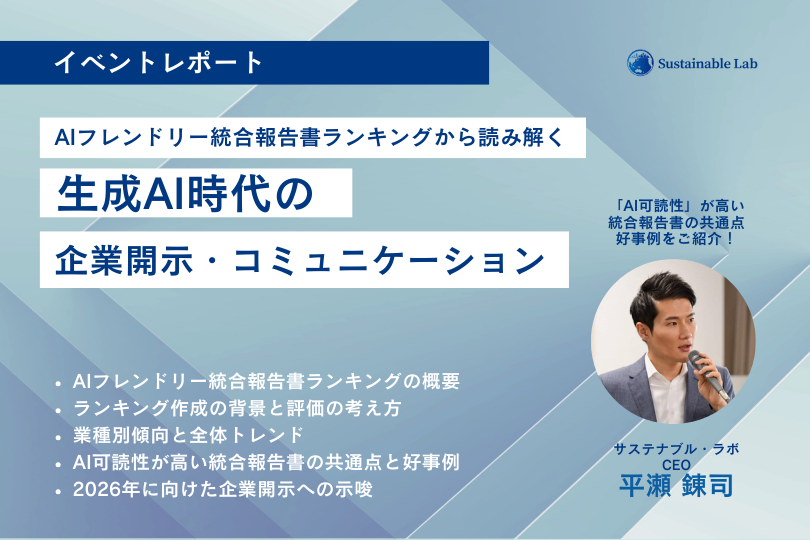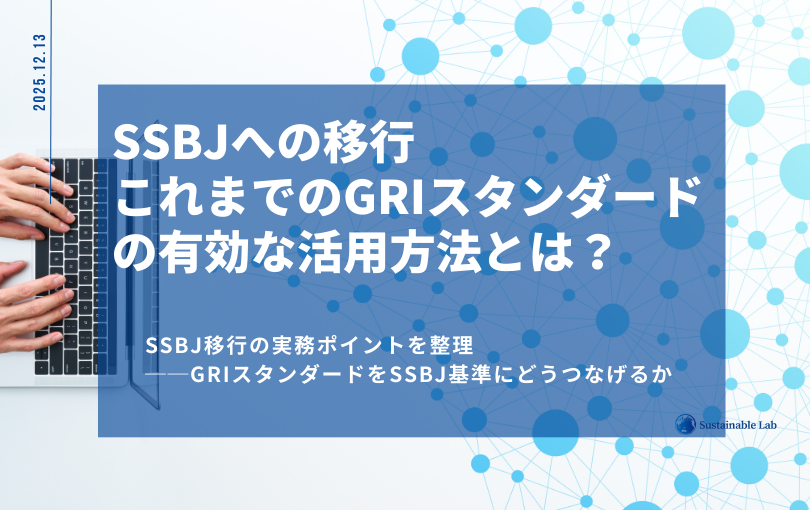2025年以降、企業のサステナビリティ開示は新しい局面に入ります。CSRDやSSBJ基準のもと、サステナビリティ情報は「連結グループ単位」での開示と財務との整合性”が求められます。
この動きに伴い、実務の現場では「連結会計ソフトウェアとの連携が必要なのか?」という問いが浮上しています。
本稿では、連結会計システムとの連携がなぜ重要なのか、どのように構築すべきかを実務目線で解説します。
1.CSRDとSSBJが求める「連結ベース開示」
● EUのCSRD
CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)は、従来の非財務報告指令(NFRD)を改め、企業のサステナビリティ情報の開示義務付け従来より詳細かつ網羅的な報告を求めるEU指令です。
適用対象はEU大企業やEU域内上場企業に限らず、EU域内に一定規模の子会社や支店を持つ非EU企業にも拡大され、条件に該当すれば日本の親会社がグループ全体のサステナビリティ情報を連結ベースで開示することを求められます。
開示データはXBRL形式* でデジタル報告が義務化され、財務諸表と同一の会計期間・タイミングでの公表が前提となります。
この「グループ単位での報告」要求は、従来の単体ベースのCSR報告やESGレポートから大きな転換点となります。子会社・関係会社を含む統合的なデータ収集体制の整備が不可欠です。
なお、企業の負担増加を考慮し、2025年3月の欧州委員会でCSRD適用開始2年延期が承認され、25年度から適用開始予定だった企業に対する義務付けは27年度分から適用となる予定です。
● 日本のSSBJ基準
日本でも、2025年3月にSSBJが「サステナビリティ開示基準(案)」を公表しました。基準案では財務情報と非財務情報を統合的に開示することを求めており、開示対象には、温室効果ガス排出量、人的資本、ガバナンス、リスク管理などが含まれます。有価証券報告書の中で財務・非財務を一体的に開示する方向も示され、2027年3月期からの実務適用が想定されています。
CSRDとSSBJで求められる開示の共通点は、「グループ連結単位」「財務との整合性」「監査可能な統制構造」の三点にあります。このため、企業グループでは非財務データも会計情報と同様に連結プロセスの中で管理する仕組みが求められています。
2.なぜ「連結会計ソフトウェア」との連携が論点になるのか
● 背景:データ量・多様性の急増
CSRD/SSBJ対応では、温室効果ガス(スコープ1〜3)、エネルギー、水資源、人的資本、取締役報酬など、多数のデータを収集する必要があります。これらは各子会社・拠点・サプライヤーから得る必要があり、手作業では集計の整合性・正確性を維持できません。
● 財務と非財務の“同時開示”プレッシャー
制度上、財務諸表と同時期にサステナビリティ報告を提出する必要があります。つまり、財務決算と非財務開示を並行して完了させるスケジュールが求められます。このため、既に「子会社データ収集・集約・消去」の仕組みを持つ連結会計ソフトウェアを活用することが、現実的な選択肢になります。
● 監査・保証対応
CSRD では、監査法人等による「限定的保証(limited assurance)」を受ける必要があります。将来的にはより保証水準の高い合理的な保証への移行が予定されています。つまり、サステナビリティ情報も財務データ同様に監査対応が必要になります。この観点でも、会計ソフトウェアが持つ証跡管理・承認フロー・アクセス統制を活かす意義は大きいと言えます。
3.連携の検討ポイント
(1)構想段階:範囲とスコープの明確化
まず、自社グループにおけるCSRD/SSBJの適用範囲を特定します。どの子会社まで報告対象か、親会社報告で免除できるかを整理し、「財務連結範囲」と「非財務データ収集範囲」を一致させることが重要です。次に、開示項目・頻度を整理します。GHG排出量や人材データなど、財務と同様の粒度・期間で集計できるかを確認します。
(2)設計段階:データ構造と連携設計
会計ソフトウェアを活かすには、子会社マスタ・勘定体系・組織階層を非財務データでも共通化する必要があります。また、入力・承認フロー、証跡、エラー検知、異常値アラートといった統制プロセスを整備することが求められます。データ統合の方式としては以下の2パターンが考えられます。
拡張型:連結会計ソフトを非財務領域に拡張し、共通基盤化する方式。既存機能を流用可能。
ハイブリッド型:サステナビリティ専用システムと会計ソフトをAPI等で連携し、柔軟性を確保する方式。
どちらを選ぶかは、子会社数・拠点の分散度・データ量・既存IT資産などで判断するといいでしょう。
(3)運用段階:継続的な管理と改善
導入後は、子会社への教育、入力マニュアル整備、定期レビューを行い、会計データと同等の運用品質を確立します。また、スコープ3やサプライヤー情報など、年々拡大する非財務データに対応できるよう、拡張性と柔軟性をもった運用体制が必要です。
監査対応では、ログ・証跡・修正履歴の保存が必須です。既存の会計統制機能を流用できると、保証プロセスが効率化します。
4.「連結会計ソフトウェア連携」はどの程度必要か
連結会計ソフトウェアとの連携は、高い必要性があるといえます。
おもな理由は以下の3点です。
制度要件との整合性:CSRD/SSBJともに「連結ベース開示」を前提としており、財務と非財務を分離して管理する体制では整合性を担保しにくい。
実務効率と精度:連結会計ソフトの既存機能(子会社データ収集・集約・整合チェック)を活用することで、入力重複・転記ミスを防げます。
監査・保証への備え:会計側の統制を非財務にも適用することで、証跡確保・承認フロー・アクセス管理の一貫性が担保されます。
ただし、すべてを会計ソフトで完結させる必要はなく、例えば、中小規模グループではExcel+クラウド収集ツールを併用して、最終的に会計システムへ集約する方法も現実的です。
● 部門間連携という実務課題
加えて、多くの企業で見られる課題が、財務部門とサステナビリティ推進部門の分業構造です。財務データは経理・財務部門が、非財務データはサステナビリティ推進やIR部門がそれぞれ管理しており、データ定義・入力ルール・システム利用権限等が分断されているケースが少なくありません。
この構造は、連携検討時の予算分担や導入主導権の不明確さにもつながります。そのため、システム検討の初期段階で、財務・サステナ・ITの三部門による横断的なプロジェクト体制を構築し、責任範囲や運用ルールを明確化することが成功の鍵となります。
5.導入・運用上の留意点
制度対応をシステム面で定着させるには、導入段階から運用までの基本ポイントを押さえておくことが重要です。主な留意点は次のとおりです。
非財務データ入力は想定以上に手間がかかる:特に海外子会社・現地拠点では、担当者教育とサポート体制の整備が不可欠。
会計側の組織変更と非財務データ構造を連動させる:子会社追加・再編時に整合性が崩れないよう、マスタ管理ルールを明確化する。
ログ・証跡の記録を徹底する:誰が・いつ・どの項目を入力/修正したかを追跡できる仕組みを整備し、監査・保証対応に備える。
段階的に導入を進める:まず主要指標(例:GHG排出量、人的資本)から着手し、順次対象範囲を拡大する。
開示対応にとどめず、経営活用を見据える:収集したデータを経営判断・リスク分析・目標管理に活用することで、システム投資の価値を最大化する。
7.まとめ「“制度対応”から“経営基盤づくり”へ」
CSRD/SSBJはいずれも「財務と非財務の統合開示」を明確に打ち出しており、連結グループ全体でのデータ統合が必須です。その実現には、連結会計ソフトウェアとの連携・活用が最も現実的な選択肢の一つといえます。
一方で、企業規模やデータ成熟度に応じて、完全統合型・ハイブリッド型など多様なアプローチが存在します。
重要なのは、制度対応を目的とするだけでなく、「サステナビリティ情報を経営に生かす基盤づくり」として位置づけることです。
今後、制度の具体化とともに、財務・非財務の境界がなくなる時代に向け、「どのようにデータを統合し、どのように経営に活かすか」—— その設計力が問われています。
【参考】
開示対応から経営情報としての活用までワンストップに対応

TERRAST powered by Uniqusでは、データ集計から分析、各種開示・レポーティング、また集計した非財務情報のモニタリング・経営情報としての活用まで、すべてのワークフローの効率化・高度化を実現します。